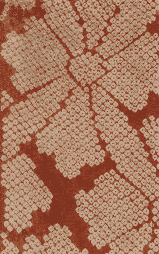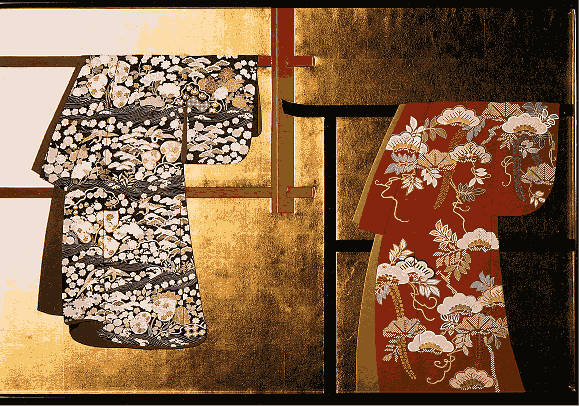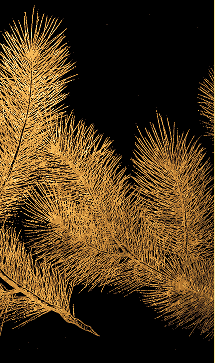| 御所解文様〈ゴショドキ〉 | |||||
| 江戸時代後期の特色ある文様に「御所解文様 」「江戸解文様 」と呼ばれるものがあります。どちらも、公家や武家の大奥、大名の奥向きの女性用の正装で、四季の草花を細やかに配し、一見風景文様と見えるものです。この名称は、近年になってつけられたもので、本来は、身分の高い女性には、キモノ全体に文様のある物を用いるところから、「総文様」と呼び、文様も次第に軽くなって、「右袖がかりの腰高文様 」、「裾文様 」などと呼ばれるようになりました。 風景文様と見える総文様も細部に注目すれば、山中の殿舎、鳥籠、飛びゆく子雀、御所車に蓑笠などの景物が見られ、これらは『源氏物語』や謡曲などをふまえた文芸文様に分類されることと気づきます。 いずれにしても、武家女性の日本の古典文芸に対する豊かな教養をうかがわせる文様です。しかし、その本来の意味は次第に失われ、単なる四季の草花で埋められた意匠となっていきました。 「御所解 」「江戸解 」の名称のおこりについては、明治維新を迎えて、公家や武家女中の伝統的な小袖類を、引き解いて売却されたからという説があります。 |
|||||
染繍小袖
江戸時代後期 木村染匠所蔵
江戸後期文化文政(1804〜1829) 白木染匠資料室所蔵
|
|||||
|
|
||
| 裾〈スソ〉文様 徳川八代将軍吉宗の統制する享保年間は、厳しい倹約の時代といわれ、元禄年間のはでやかさは影をひそめます。 その頃作られた小袖の文様構図は、これまでの総文様に代わり、文様を下方に置く、裾文様が多くなってきました。 裾文様が好まれるようになった理由は、そうした倹約のほかに帯幅がしだいに広くなり、髪型も大きく結うようになったことが上げられます。髪型や帯と共に、全体のバランスを保つため、裾文様はふさわしいと考えられたのでしょう。 裾文様をほどこす位置は、年齢の高くなるほど低く、地味なものになっていきます。宝暦年間には、打掛などの他のキモノは裾文様が取りあげられました。 この裾文様が、現在の留袖のもととなります |
|||
|
|
||
| 誰が袖〈タガソデ゙〉 誰が袖は、小袖の文様に直接関わるものではありませんが、小袖を語る上で、興味深いものとして、ここに紹介しておきます。 平安の頃から、キモノに香を焚きしめていたことは知られていますが、時代が下がるとその習慣は、三角の小さな匂い袋を懐中に偲ばすことにかわっていきました。その匂い袋のことを"誰が袖"と呼び、移り香を楽しんだといわれています。『古今和歌集』の第一巻、春歌上にも"誰が袖"を詠んだ歌が記されています。 また、桃山時代から江戸時代初期にかけて作られた、衣桁〈イコウ〉に掛けた"贅を尽くした美しい小袖"を、金屏風に描いたものを「 誰が袖屏風 」と呼んでいます。その後、美しい小袖の裂地を屏風に直接貼りつけた「 誰が袖屏風 」も見られます。 さらに、その"誰が袖"を意匠とした小袖文様まで作られたといいます。 これらのことから、近世の小袖がいかに美しく、魅力的な精彩を放つものであったかがうかがえます。中でも「 誰が袖屏風 」の出現は、着用を離れて小袖そのものを鑑賞するという風潮を庶民の間にも広めたようです。天和・貞享・元禄の頃に見られる「小袖幕 」も、その表われではないでしょうか。 |
||
|
||
|
||
誰が屏風 |
||
| 琳派文様 | |
|
琳派とは、いうまでもなく江戸時代初期の俵屋宗達に始まり、中期の尾形光琳によって大成された装飾画の流れを言います。 草花の個々の形体は、自然の優美な姿より造形的な形そのものの面白さが強調されていますが、描写自体には深い観察の目がそそがれています。また、光琳自身も画家としての面と初期のころより最晩年まで工芸デザインと深い関わりを持ち続け創作活動・作品においても工芸デザイン的な内容を取り入れるによって、琳派が完成されていったと思われます。そして この琳派が日本の装飾文化にはたしてきた役割は計り知れないものがあります。 |
|
|
|
| 蒔絵文様 | |
|
桃山時代になり、庶民文化の手の届くものではなかった蒔絵が、新興町衆の身近なものとなり「烏丸もの」と称されるものが出現しました。高台寺蒔絵・南蛮蒔絵などの多くはこのような町蒔絵師によって生み出されたものです。 これら町蒔絵師の作風は、技法に裏打ちされた意匠、特にその装飾効果に重きをおくものとなり、京蒔絵の伝統となって後世に伝えられてまいりました。これらの蒔絵をモチーフとして装飾デザインが生み出されて行くことになります。 |
|
|